仮想通貨ブームの影響で「ビットコインに投資すべきか?」と悩む人は多いと思います。しかし、結論からいえば、資産形成のメイン戦略としては投資信託(インデックス投資)で十分です。この記事では、その理由を初心者向けにわかりやすく解説します。
1. ビットコインとは?投資対象としての特徴
ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、中央銀行や政府の管理を受けない通貨です。特徴としては以下のような点があります。
- 発行上限が決まっており(2,100万枚)、希少性がある
- 値動きが非常に激しく、1日に数%〜数十%動くこともある
- 世界中で24時間365日取引される

確かに将来性はありますが、その分リスクも非常に高く、短期間で資産が大きく増減する可能性があります。
ビットコインは2009年に誕生した最初の暗号資産であり、誕生から10年以上が経過してもなお市場の中心的存在です。金(ゴールド)のように発行量が限られているため「デジタルゴールド」とも呼ばれています。
ただし、ゴールドと決定的に違うのは「価格の安定性」です。金は数十年単位で見れば比較的安定していますが、ビットコインは誕生から短期間で数十倍に上昇したり、一気に半分以下に暴落することが何度もありました。
また、通貨としての普及度もまだ限定的で、実際に日常生活で「ビットコインで支払う」機会はほとんどありません。つまり「投資対象」としての色が強く、長期の資産形成に必須の存在とは言えないのが現状です。
2. インデックス投資との比較
インデックス投資(S&P500やオルカン)は「世界経済全体の成長に長期的に乗る」投資です。一方ビットコインは、需給バランスと投機的な動きで価格が大きく上下します。
- インデックス投資:年平均4〜7%程度のリターンを狙える(過去データより)
- ビットコイン:数年で数倍になることもあれば、半値以下になることもある

長期で「資産形成」を目的にするなら、インデックス投資のほうが再現性が高いと言えます。
インデックス投資は、投資信託やETFを通じて「市場全体」に分散投資する手法です。たとえばS&P500は米国を代表する500社に、オルカンは全世界の数千社に分散されます。そのため、一部の企業が倒産しても影響が小さく、安定した成長を取り込めます。
一方、ビットコインは分散投資ではなく「1つの資産」に集中投資することになります。確かに短期的に急騰する魅力はありますが、長期で安定したリターンを求める人にとっては再現性が低いです。
実際、過去20年でインデックス投資は平均年率4〜7%の安定した成長を示してきましたが、ビットコインは同じ期間に数百倍になった反面、数年単位で70〜80%下落することもありました。資産形成を目的にするなら「安定した複利」を狙えるインデックス投資の方が合理的です。
3. ビットコインに投資するリスク
ビットコイン投資を考える際は、以下のリスクを理解しておく必要があります。
- 価格変動リスク:2021年には1BTC=約700万円を超えましたが、翌年には200万円台まで急落しました。株式市場では考えにくい変動幅です。
- 規制リスク:中国では仮想通貨の取引が禁止され、アメリカや日本でも課税ルールが頻繁に変わります。規制次第で市場環境が大きく変化します。
- セキュリティリスク:大手取引所がハッキングされ数百億円規模の資産が流出した事例もありました。銀行預金のような「預金保護制度」は存在しません。

これらのリスクは投資信託にはほぼ存在しません。
このように、インデックス投資にはない不確実性が多いため、初心者にとっては精神的負担が大きくなりがちです。
4. 長期投資でビットコインは必要ない理由
資産形成の王道は「長期・分散・積立」です。これを実現できるのがインデックス投資です。ビットコインのような値動きの激しい資産を組み込むと、暴落時に不安になり、投資をやめてしまうリスクがあります。
長期投資の基本は「市場全体に分散し、時間を味方にする」ことです。インデックス投資はまさにこの条件を満たしており、ほったらかしでも成果が出やすい仕組みです。一方でビットコインは長期保有しても値動きが読めず、暴落時に「怖くなって売却してしまう」投資家が多いのも事実です。途中で撤退すれば、せっかくの成長も取り込めません。
さらに、資産形成の目的は「資産を増やすだけでなく守ること」にもあります。生活資金や老後資金を考えたとき、価格が数分の1になるリスクを抱えた資産をコアに据えるのは現実的ではありません。
つまり「再現性が低い」「精神的に不安定になりやすい」ため、長期投資を続けたい人にとっては必要ないと言えるのです。
5. どうしても投資したいなら「余剰資金の一部」で
とはいえ、「ビットコインに興味がある」「仮想通貨にも触れてみたい」という人もいるでしょう。その場合は、全資産の1〜5%程度に抑えるのが現実的です。「最悪ゼロになっても生活に影響がない金額」であれば、将来の成長を期待して少しだけ持ってみるのはアリです。

とはいえ、私自身は多少持っています。今計算したら全体の5%を超えていましたが、初期投資額は20万円でした。
ここからは個人的な考えが非常に強くなるので、共感していただける方だけ参考にしていただければ・・・という話にはなりますが、ビットコインに投資したのは、ビットコインへの投資というよりは、「WEB3の新しい技術に触れておきたい」という意味合いが強いです。
ビットコインというと「デジタルゴールド」や「暗号資産」と言われるので、投資対象とみられることが多いですが、ブロックチェーン技術を使っている点が面白いと思っています。
ブロックチェーンとは、「取引データを時系列にまとめて鎖のようにつないで管理する仕組み」です。
銀行のような中央管理者を介さず、世界中のコンピュータが同じ台帳を共有することで「改ざんが難しく、透明性の高い取引」を実現しています。
ビットコイン自体は原初の暗号通貨であるため、取引コストも高く、ビットコインそのものを通貨として利用することは現実的ではない気がしますが、ブロックチェーン技術を利用した他の暗号資産も続々と出てきています。特に、イーサリアムはスマートコントラクトという条件が満たされたら自動で処理が実行される仕組みを組み込むことができます。
一昔前に「NFT」が界隈で流行しましたが、あれもスマートコントラクトという仕組みを利用したものです。
また、近年ではJPYCという金融庁の認可を受けたステーブルコインが発行される見込みです。ステーブルコインとは、既存の通貨を裏付けにに、通貨と価値を連動させた暗号通貨です。JPYCは日本円と連動するよう設計されているので、1JPYC=1円として価値が推移し、日本円と同様に決済手段として利用することが認められています。
 ブロックチェーン初心者必見!1円=1JPYCの仕組みと使い方
ブロックチェーン初心者必見!1円=1JPYCの仕組みと使い方
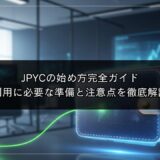 JPYCの始め方完全ガイド|利用に必要な準備と注意点を徹底解説
JPYCの始め方完全ガイド|利用に必要な準備と注意点を徹底解説

JPYCは暗号通貨というよりは、イーサリアムやAVAX上で動かすことができるERC20規格のトークンなのですが細かいことは気にしなくて大丈夫です!
このJPYCを実際に使うにも、ウォレットというアプリケーションなりで自分自身でJPYCを管理する必要がありますが、ここにもブロックチェーン技術が使用されています。
また、ブロックチェーン技術を応用したものでDeFiというサービスもあります。これは、Decentralized Finance(分散型金融)の略で銀行や証券会社などの仲介を介さず、ブロックチェーン上で誰でも利用できる金融サービスの総称です。DeFiの活用例としては以下のものがあります。
- 分散型取引所(DEX)
銀行口座なしで仮想通貨を交換可能。 - レンディング(貸付・借入)
暗号資産を担保に別の資産を借りられる。 - イールドファーミング(利回り運用)
DEXに流動性を提供し、手数料や報酬を得る。

インターネットも開発された当初は何のために使うの?って思われていた見たいですが今やなくてはならない存在です。ブロックチェーン技術も今後そうなる可能性を鑑みると、今のうちに遊び半分で触っておくのがいいと個人的には思っています。
まとめ:ビットコインは必須ではない。インデックス投資を続けよう
ビットコインは将来性がある一方で、値動きが激しく、長期の資産形成に必要不可欠な存在ではありません。むしろ、NISAを活用してインデックス投資を継続する方が圧倒的に再現性が高い戦略です。
- 資産形成の土台:インデックス投資(オルカン・S&P500など)
- ビットコイン:やるなら「お試し程度」の余剰資金で
このスタンスを守れば、安心して長期の資産形成を続けることができます。
資産形成において重要なのは「安定して再現性のある方法を続けられるかどうか」です。ビットコインは面白い投資対象ではありますが、価格変動が大きすぎて長期の資産形成には不向きです。NISAを使ってオルカンやS&P500に積立投資するだけで、数十年後には大きな資産を築ける可能性が高いと過去のデータが示しています。
つまり、ビットコインは「なくても問題ない資産」であり、どうしても持ちたいならほんの一部にとどめましょう。王道はあくまでインデックス投資です。

最後にブロックチェーン技術に触れましたが、基本的なスタンスは投資初心者にビットコインは不要です。ただし、最新の技術に触れるという意味で趣味の範囲で触ることはいいと思います。



