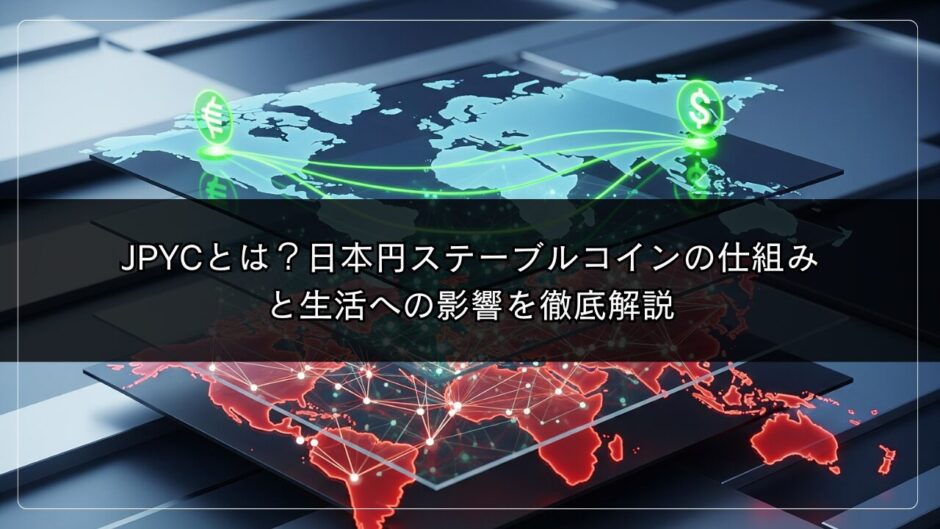最近注目を集めている「JPYC(日本円ステーブルコイン)」。仮想通貨の一種ですが、ビットコインやイーサリアムのように価格が乱高下するものではなく、常に1円=1JPYCの価値を持つことを目指しています。この記事では、JPYCの仕組みや裏側でどのように安定性が保たれているのかを詳しく解説します。
JPYCは「日本円の価値をそのままデジタル化した仮想通貨」です。ビットコインのように価格が数%〜数十%単位で上下することはなく、1円=1JPYCで安定しているため、仮想通貨の「ボラティリティが高くて怖い」というイメージとは対照的です。
特に、投資対象というよりも「決済・送金・交換手段」としての側面が強いため、暗号資産に馴染みのない人でも使いやすいのが大きな特徴です。JPYCは日本国内での利用を意識して設計されているため、今後は電子マネーやQR決済の代替・補完手段になる可能性も期待されています。
 日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」とは?
日本初の円建てステーブルコイン「JPYC」とは?

前回の記事をさらに深ぼる形で解説していきたいと思います!
JPYCの基本的な仕組み
JPYCは「日本円と連動するステーブルコイン」です。発行された1JPYCは常に1円として利用できるよう設計されています。そのため、暗号資産でありながら値動きの大きなリスクがなく、電子マネーや銀行預金のように「安定した価値の保存・送金手段」として利用できます。
JPYCはEthereumやPolygonといった複数のブロックチェーン上で発行されており、ウォレットを持てば誰でも利用できます。
発行体のJPYC株式会社が「1円に相当する資産を裏付けにしてJPYCを発行」することで、円と同じ価値を維持します。
ユーザーがJPYCを購入すると、その分の日本円が信託銀行などに保全され、同額のJPYCが新規発行されます。逆にJPYCを償還(現金化)する場合は、そのJPYCをバーン(焼却)し、対応する日本円が払い戻される仕組みです。
この流れによって市場に出回るJPYCの総量と保有資産のバランスが常に一致し、安定性が確保されます。
裏付け資産と信託スキーム
JPYCが「1円=1JPYC」の価値を維持できるのは、発行されたJPYCの裏側に日本円建ての安全資産(銀行預金や日本国債)が存在するからです。発行体のJPYC株式会社は、ユーザーから受け取った日本円を信託銀行を通じて保全し、その資産を担保としてJPYCを発行します。
この仕組みにより、仮にJPYC株式会社が経営破綻しても、利用者のお金は信託銀行で保全されているため返還される仕組みになっています。これはステーブルコインの安全性を担保する重要なポイントです。
JPYCの安心感を支えるのが「信託保全スキーム」です。
JPYC株式会社は利用者から預かった円をそのまま自社の口座で保管するのではなく、信託銀行を通じて分別管理します。これにより、万が一発行体が倒産しても利用者の資産は守られる仕組みになっています。
さらに、裏付け資産には現金だけでなく日本国債など安全性の高い資産も活用されるため、ステーブルコインとしての信頼性を高めています。これは、世界で流通するTether(USDT)やUSD Coin(USDC)といった米ドル連動型ステーブルコインと同様の考え方であり、「法定通貨を裏付けにして安定性を確保する」というのが基本の仕組みです。
JPYCの利用方法
1. 支払いに使う
すでに一部のECサイトやオンラインサービスでは、JPYCによる支払いが可能になっています。Amazonギフト券やQUOカードPayなどへの交換も可能で、「使える場所」が着実に広がっています。特に「1円単位で利用できる」という特徴は、暗号資産の中でも珍しく、日常生活での決済手段として親和性が高いといえます。

後払い手段としてクレジットカードの支払いが普及していますが、これがJPYCに置き換わるという予想をする人もいます!
2. ブロックチェーン上で送金する
JPYCはEthereumやPolygonといったブロックチェーン上で利用可能です。そのため、従来の銀行振込に比べて、迅速かつ低コストでの送金が可能になります。特に海外送金においては大きなメリットがあります。
ブロックチェーン上で動作するため、銀行の営業時間や国境に縛られることなく24時間365日で送金できます。例えば、国内銀行送金では数百円かかる手数料も、JPYCの送金なら数円〜数十円で済む場合があります。特に海外送金では「速い・安い」というメリットが際立ちます。
3. DeFiやNFTで活用する
JPYCはブロックチェーン上で動作するため、DeFi(分散型金融)やNFTの購入などにも利用できます。例えば「値動きのある仮想通貨は怖いけど、安定した円建て資産でDeFiを触ってみたい」という人に適しています。
JPYCはブロックチェーンと親和性が高いため、DeFiでの運用やNFT購入の基軸通貨として使えるのも魅力です。ボラティリティがないので「値動きに左右されずにDeFiの金利だけ享受したい」といった使い方が可能です。
JPYCのメリット
- 価格が安定している:1円=1JPYCで常に利用できる
- 送金がスピーディー:ブロックチェーンを活用することで数分〜即時送金が可能
- 信託保全で安心:発行体に問題があっても資産は守られる
- DeFiやNFTでの利用が可能:円建て資産でブロックチェーンの世界に参加できる
JPYCの課題や注意点
まだ新しい取り組みであるため、利用できる店舗やサービスは限定的です。また、日本国内の規制も整備途上であり、今後の法制度によっては仕組みが変わる可能性もあります。さらに、発行体の信頼性や流動性の確保といった点は投資家・利用者ともに注視すべきポイントです。
一方で、JPYCには課題もあります。
まず、利用できるサービスや店舗がまだ限られているため、日常生活での普及はこれからの課題です。
また、日本国内ではステーブルコインの法整備が進んでいる最中であり、規制の方向性によっては制度変更や新ルールの導入があり得ます。
さらに、暗号資産として利用する以上は「ウォレット管理」や「秘密鍵の紛失リスク」も避けられません。安全性は高いものの、使い方を誤ると資産を失うリスクがある点には注意が必要です。
JPYCと他のステーブルコインとの比較
ステーブルコインといえば、世界的には「USDT(Tether)」や「USDC(USD Coin)」が有名です。これらはいずれも米ドルと価値が連動しており、仮想通貨市場の基軸通貨として使われています。一方、JPYCは日本円と連動している点で大きな違いがあります。以下では、それぞれの特徴を比較してみましょう。
1. 通貨の裏付け
- JPYC:日本円に連動。裏付け資産は信託銀行で分別管理される円や国債。
- USDT:米ドル連動。裏付け資産には現金や商業手形などが含まれ、過去には透明性を巡る議論があった。
- USDC:米ドル連動。米国の規制に準拠し、準備資産は現金および米国債で構成。透明性が高い。
2. 主な利用シーン
- JPYC:日本国内での決済、ギフト券や電子マネーへの交換、DeFi/NFT取引。
- USDT:世界最大規模の取引量を誇り、暗号資産取引所での基軸通貨として利用されることが多い。
- USDC:DeFiやNFT市場で広く利用。規制準拠の安心感から、機関投資家の利用も増加。
3. 安全性・信頼性
- JPYC:日本の法制度に基づき、信託保全で安全性を担保。日本人ユーザーには馴染みやすい。
- USDT:世界で最も利用されているが、準備資産の透明性について過去に疑念が持たれたことがある。
- USDC:定期的に監査報告を公開しており、透明性の高さから信頼度は比較的高い。
4. 利用範囲
- JPYC:国内利用に強みがあるが、グローバル利用はまだ限定的。
- USDT/USDC:グローバルに利用可能で、仮想通貨市場における取引量・流動性は圧倒的。
USDTやUSDCは「世界の仮想通貨市場での取引基軸通貨」としての役割が強く、グローバル利用に適しています。一方、JPYCは「日本円のデジタル化」としての側面が強く、日本国内の決済や生活に根付いた使い方に期待ができます。つまり、JPYCは日本人にとって身近な生活通貨、USDTやUSDCはグローバル金融の中核、と役割が分かれていると言えるでしょう。
まとめ:JPYCは「円のデジタル化」を実現する存在
JPYCは、仮想通貨のメリット(迅速な送金・国際的な利用)と日本円の安定性を両立させた新しい仕組みです。現段階では投資でリターンを得る対象ではなく、「使いやすさ」「利便性」を提供する通貨と考えるのが正しいでしょう。今後、対応するサービスが増えれば、私たちの生活に身近な存在になる可能性は十分にあります。
JPYCは、日本円の安定性とブロックチェーンの利便性を融合させた新しい仕組みです。
現状はまだ利用範囲が限定的ですが、普及が進めば「キャッシュレス決済の選択肢」や「Web3時代の日本円のデジタル版」として生活に大きな影響を与える可能性があります。
投資対象というよりも「安定した円建てのデジタル通貨」として捉え、送金・決済・ブロックチェーン利用のハブとして活用できるかどうかが今後の注目ポイントになるでしょう。
これからのキャッシュレス社会やWeb3時代において、JPYCがどのように普及していくのか注目していきましょう。