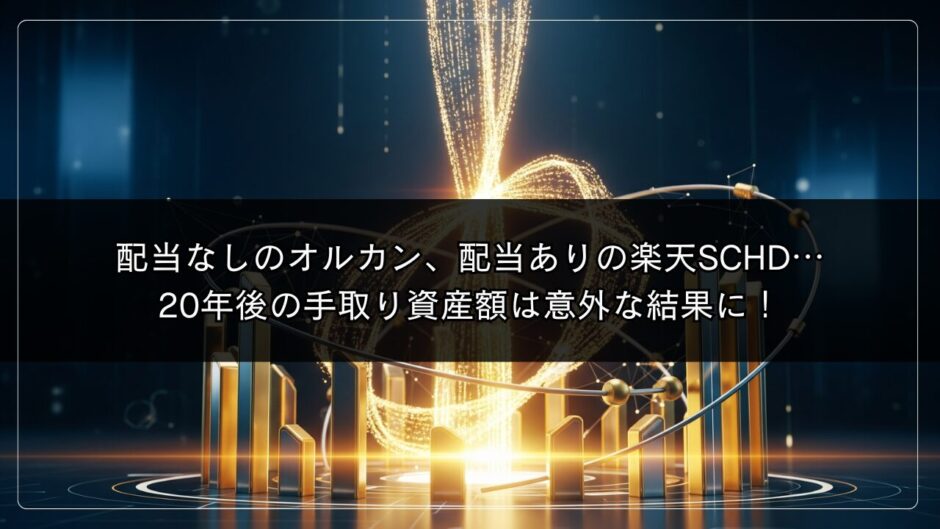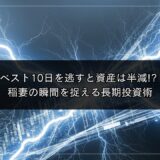人気の「オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)」と「楽天SCHD(楽天・米国配当株式インデックス・ファンド)」。今回は、NISA枠1,800万円を使い切った後の特定口座運用まで含めて、20年間積立した場合の最終的な手取り資産額を比較します。
比較条件
- 毎月積立額:10万円(年間120万円)
- 投資期間:20年間(240ヶ月)
- オルカン:年率10.9%(信託報酬0.05775%込)
- 楽天SCHD:年率11.18%から信託報酬0.2%控除 → 実効10.98%
- 楽天SCHDは年4回の分配金を再投資(国内籍投信のためNISA内は非課税)
- NISA枠:生涯投資上限1,800万円
- NISA枠消費後は特定口座で新規投資(利益に20.315%課税)
- 為替や為替手数料は考慮しない
前提としては、このように定義しました。
SCHDの手数料は0.1238%になっていますが、見積もれない隠れコスト分がおそらくはオルカンよりは多いだろうという点を考慮して0.2%としています。
オルカンについても同様に隠れコストを見込むべきですが、楽天オルカンの投資信託保有ポイント分の還元を考慮していないので、信託報酬そのままで考えています。
オルカンの年率10.9%はかなり強気にみえますが、SCHDの設定2013年10月以降の年平均リターンになります。
当記事では、「これだけ投資したらこのくらい増える」というよりは、「純粋にオルカンとSCHDを比較したらどうなるか?」というところで考えて見たいので、実績に近い数値を参照しました。
NISA枠消費のスピード
- オルカン(無分配型):毎年120万円 → 15年で1,800万円に到達
- 楽天SCHD(分配金再投資型):年間120万円+配当再投資分(平均約24万円) → 約12.5年で1,800万円に到達
楽天SCHDは配当再投資分でもNISA枠を使うため、オルカンより約2年半早く枠を使い切ります。

オルカンは分配金がないから損!ということはなくて、組み込まれた株式の配当は自動で再投資されて基準価格に織り込まれています。むしろNISA枠を消費しない分お得です!
シミュレーション結果(20年後の資産額)
| 投資先 | NISA部分(非課税) | 特定口座部分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| オルカン | 約5,865万円 | 約968万円 | 約6,833万円 |
| 楽天SCHD | 約5,359万円 | 約1,227万円 | 約6,586万円 |
結果の読み解き
1. 最終的な総資産額はオルカンがやや優位
税引き前では両者ほぼ互角ですが、楽天SCHDはNISA枠消費が早く、特定口座部分が多くなる分だけ課税されます。その結果、20年後の手取り資産額ではオルカンが約250万円ほど多くなりました。
特定口座で運用する分の分配金には20.315%の税金がかかります。
年間4回分配金として入金されるお金から税金が毎回差し引かれる影響は大きいですね。
2. 投資スタイルの違い
オルカンは全世界分散型で、配当を出さずに自動で複利運用します。
楽天SCHDは米国高配当株に集中し、配当収入を実感できる代わりに枠効率は低めです。
オルカンはインデックス投資ですが、SCHDはアクティブ投資です。
やっていることが全然違います。
楽天SCHDは設定来の運用成績がよく、人気がありますが、前提として9割のアクティブ投資はインデックス投資に勝てないということ。
また、インデックス投資に勝っているアクティブファンドでも期間を長くとればインデックスに劣後することが一般的であること。
こういったことを理解した上で投資をするようにしたいところです。
まとめ
- 最終資産額はどちらも6,500万円超だが、手取りはオルカンがやや有利
- NISA枠を効率よく使いたいならオルカン、配当を重視するなら楽天SCHD
- 長期積立では「税効率」と「非課税枠の消費スピード」も重要な判断基準になる
資産成長を最大化したいなら、NISAつみたて投資枠でオルカンをコツコツ積み立てる戦略が有力です。配当収入を重視するなら、楽天SCHDを一部組み合わせるのも選択肢となります。

以降は補足として、投資初心者には少し難しい概念になりますが、理解しておいた方が今後の資産形成に役立つ内容なので、少し詳しく解説させてください!
補足:株式の「配当金」と投資信託の「分配金」:その本質的な違いと基準価額への影響
投資において「配当」という言葉はよく耳にしますが、その対象が株式なのか投資信託なのかによって、その性質は大きく異なります。この違いを理解することは、資産形成戦略を立てる上で非常に重要です。
まず、株式の配当金は、企業が事業活動で得た利益の一部を、その企業の株主に還元するものです。配当の有無や金額は、企業の業績や経営方針によって決まり、一般的には年1〜2回支払われます 。重要な点として、配当金が支払われたからといって、その企業の株価(元金)が直接的にその分だけ下がるわけではありません。これは、企業が利益を株主還元として「外部」に支払うためであり、企業の事業活動から生み出された「新たな収益」が株主へと分配されるという側面が強いです。
一方、投資信託の分配金は、投資信託の運用によって得られた収益(利子、配当、売買益など)の一部、または元本から投資家に支払われるものです 。投資信託ごとに支払いの頻度(毎月、年1回など)や方針が異なり、目論見書やファンド詳細画面などで確認することができます 。株式の配当金と決定的に異なるのは、投資信託の場合、分配金が支払われるとその分だけ基準価額が下がるという点です 。これは、分配金がファンドの資産(純資産)を取り崩して支払われるためです 。つまり、投資信託の分配金は、ファンドの内部から資産が流出する形となるため、その時点でのファンドの価値が減少します。
この点は、特に投資初心者にとって誤解されやすい部分です。投資信託の分配金は、株式の配当金のように「追加の収益」として捉えられがちですが、実際には「ファンド内資産の払い戻し」という側面が非常に強いです。特に、元本から支払われる「元本払戻金(特別分配金)」は非課税ですが 、これは文字通り投資元本の一部が返還されているだけであり、資産が増えているわけではありません。たとえ課税対象となる「普通分配金」であっても、基準価額がその分下がるため、ファンド全体の純資産価値は変わりません。したがって、高分配金利回りの投資信託が必ずしも高リターンであるとは限らず、むしろ元本を毀損している可能性すらあるという警告につながります。投資信託の分配金は、ファンドの純資産から支払われるため、分配金が支払われた分だけファンドの価値が減少するという本質を理解することが、適切な投資判断の第一歩となります。
補足2:投資信託の「内部再投資型」と「分配金受取型・再投資型」のメカニズム
投資信託の分配金には、その取り扱い方によって大きく3つのメカニズムが存在します。
- 分配金受取型: 投資信託から支払われた分配金を、現金として投資家が受け取る方式です 。この場合、受け取った現金は投資家の自由に使うことができますが、その都度課税対象となり、その分、複利効果の恩恵を直接的に享受することはできません。投資家が手元に資金を必要とする場合には適していますが、資産の最大化を目指す長期投資には不向きな側面があります。
- 分配金再投資型: 受け取った分配金を現金として引き出さず、そのまま同じ投資信託の追加購入に充てる方式です 。これにより、投資口数が増加し、その後の基準価額上昇による複利効果を期待できます。しかし、この「分配金再投資型」であっても、分配金が支払われる時点で基準価額は下落し、分配金は一度投資家の「所得」として認識され、課税対象となります 。その後、税引き後の金額が再投資されるため、税金分だけ再投資に回せる金額が減少します。また、分配金を受け取らないまま再投資したにもかかわらず、基準価額が下落してしまうと、再投資した分もあわせた評価損が出てしまう可能性もあります 。これは、複利効果が税金によって一部阻害されることを意味します。
- 内部再投資型(無分配型): 投資信託が運用によって収益を上げた場合でも、分配金を一切支払わず、ファンド内で自動的に再投資する方式です。これにより、基準価格が上昇します。投資家の手元に現金としての分配金は渡りません。本レポートの比較対象であるオルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)は、この「内部再投資型」に該当し、過去の分配金実績は0円です 。
この「内部再投資型」は、長期的な資産形成において極めて大きなメリットをもたらします。分配金が投資家の手に渡らないということは、その時点での課税が発生しないことを意味します。これにより、本来課税されるはずの金額も元本として運用され続け、複利効果が最大限に高まります。これは、分配金が一度課税されてから再投資される「分配金再投資型」と比較して、長期的な資産成長において決定的な税効率上の優位性をもたらします。税金が引かれない分、より多くの元本が複利の力で増え続けるため、最終的な資産額に大きな差が生じることになります。言葉は似ていても、「分配金再投資型」と「内部再投資型」は、税制面と複利効果の点で根本的に異なるため、この点を明確に理解することが重要です。
補足3:資産形成における「時間」と「複利効果」の重要性:「つみたて投資」の意義
資産形成とは、「貯めながら殖やす」という概念であり、将来の自分や家族のために、計画的に資金を貯めつつ、その資産を育てていくプロセスを指します 。このプロセスにおいて、特に重要な役割を果たすのが「時間」と「複利効果」です。
毎月、または定期的に一定額を投資対象に拠出する「つみたて投資」は、時間という要素を最大限に味方につけ、価格変動リスクを抑えながら、計画的な資産形成を可能にします 。これは、投資のタイミングを計る必要がなく、市場の変動に左右されにくいというメリットがあります。価格が高い時には少なく買い、安い時には多く買う「ドルコスト平均法」の効果により、平均購入単価を平準化し、長期的なリスクを軽減します。
そして、複利効果は、投資によって得られた利益を再投資することで、その利益がさらに利益を生み出す効果を指します。この「利益が利益を生む」という連鎖は、特に長期投資において絶大な力を発揮し、資産を雪だるま式に増やす最大の原動力となります。アインシュタインが「人類最大の発明」と評したとも言われる複利の力は、投資期間が長くなるほどその効果が指数関数的に増大します。
「つみたて投資」は、ドルコスト平均法により高値掴みのリスクを軽減し、長期にわたる継続は「時間」という最大の要素を最大限に活用します。この「時間」と「複利効果」の組み合わせが、内部再投資型の投資信託で最も効率的に機能します。なぜなら、内部再投資型は分配金による課税や再投資の手間がなく、得られた収益が自動的かつ無駄なく元本に組み込まれ、複利の鎖が途切れることなく成長し続けるからです。一方、分配金を都度受け取る方式では、複利の鎖が途切れるだけでなく、その都度税金が発生し、再投資に回せる金額が減るため、複利効果が弱まります。この相乗効果の有無が、最終的な資産額に大きな差をもたらします。20年という長期の積立投資を想定するユーザーの目的を達成するためには、この複利効果を最大限に引き出す戦略が不可欠となります。