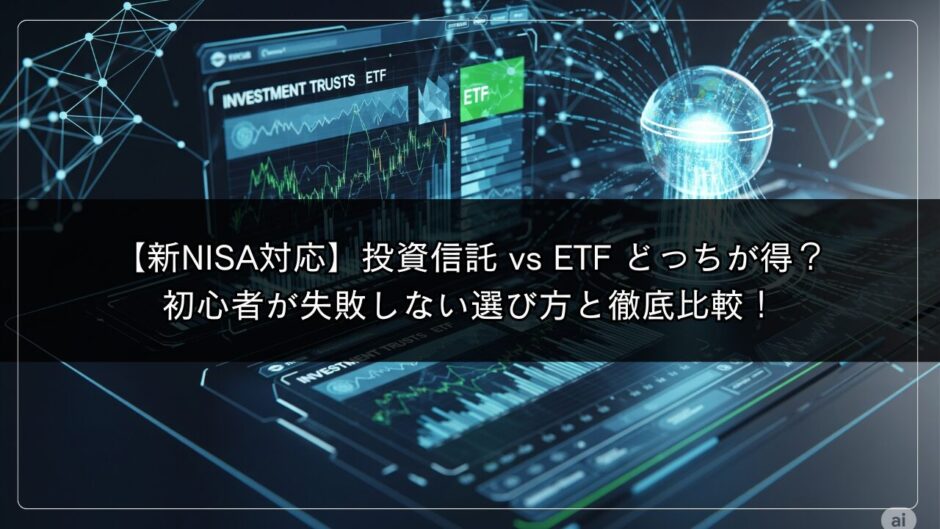NISA(少額投資非課税制度)は、投資初心者でも手軽に始められる資産運用の強い味方です。
でも「投資信託とETF、どちらでNISA枠を使えばいいの?」と迷う方も多いはず。
この記事では、両者の違いやメリット・デメリットを比較し、あなたにぴったりの選び方を解説します。

私の結論は「投資信託」です!※オルカンやS&P500などの指数に連動したインデックス投資を行う前提です。
投資信託とETFの基本的な違い
- 投資信託
・1日1回決まる基準価額で取引(リアルタイムではない)
・少額からコツコツ積み立てしやすい
・新NISA積立投資枠で選べる商品が多い - ETF(上場投資信託)
・証券取引所に上場している投資信託の一種
・株式と同じようにリアルタイムで売買できる
・購入は証券会社の取引画面から注文する
・配当(分配金)が出る商品も多い
ETFは上場しているので、その金額で売買します。1単元が34,300円の投資信託の場合、34,300円ないと購入できません。
対して、投資信託であれば、基準価格が34,300円であっても、30,000円分購入するということが可能です。
その点で、毎月定額を積立購入するというドルコスト平均法に則った投資がしやすいというメリットがあります。
【比較表】投資信託とETFの違い
| 項目 | 投資信託 | ETF |
|---|---|---|
| 購入方法 | 証券会社・銀行など 1日1回価格決定 | 証券会社 株式と同じようにリアルタイム取引 |
| 最低投資金額 | 100円から可能な商品が多い | 1口単位で、数千円~数万円から |
| 積立投資 | 簡単に設定できる(自動積立OK) | 証券会社による(自動積立対応のETFも増加中) |
| 売買コスト | 購入・売却時の手数料は基本無料(ノーロード) | 売買ごとに手数料がかかる(証券会社による) |
| 分配金・配当 | 自動的に再投資される商品が多い 受け取りか再投資か選択できるものも | 現金で受け取れる商品が多い |
| 値動き | 1日1回の基準価額で反映 | 株価のようにリアルタイムで変動 |
| NISAとの相性 | つみたて投資枠で選べる商品多数 自動積立に最適 | 新NISA(成長投資枠)で購入可能 高配当ETFも人気 |
この中で、投資成績に与える影響で一番大きいのが分配金の受け取り方法についての部分です。
ETFの場合、分配金は口座に入金されます。しかし、投資信託の場合、口座に入金されるものもあれば、内部で自動再投資してくれるものもあります。
内部で自動再投資してくれるものをNISA枠で購入できるというのが最大のメリットになります。
新NISAは生涯の枠が1,800万円までと決められています。この1,800万円は評価額ベースではなく、購入額ベースです。
なので、毎月10万円投資を15年続けて1,800万円分の投資信託を購入し、その評価額が3,000万円になっていたとして、それ全てを売却したとしても、3,000万円全額非課税で受け取ることができます。
購入額ベースでNISA枠を消費する。この前提を覚えておいてください。
投資信託の「自動再投資」には2種類ある!わかりやすく解説
投資信託には「自動再投資」という仕組みがある、と聞いたことがある方も多いと思います。
実はこの「自動再投資」には、2つのパターンがあります。それぞれどんな違いがあるのか、具体例を交えてやさしく解説します。
1. 分配金を自動で投資信託の購入に使うパターン
まず一つ目は、分配金が出たときにそのお金を現金として受け取るのではなく、自動的に同じ投資信託の追加購入にあててくれるパターンです。
- 例えば、あなたが投資信託を100万円分持っていたとします。
- この投資信託から、1年間で3万円の分配金が出ました。
- 「自動再投資」を選んでいる場合、この3万円をそのまま受け取らずに、新たに3万円分の投資信託を買ってくれます。
- つまり、最初の投資額100万円+追加で買った3万円=合計103万円分の投資信託を保有することになります。
- この時、分配金は現金としては手元に入りませんが、持っている投資信託の量がどんどん増えていくイメージです。
- もし投資信託の価格(基準価額)が変わらなければ、評価額は103万円となります。

1,800万円の枠を消費した状態の分配金再投資は特定口座での買付になります。
2. 分配金がそもそも発生せず、基準価額が上昇するパターン
もう一つのパターンは、そもそも分配金が出ない代わりに、その分だけ投資信託自体の価値(基準価額)が上がっていくタイプです。
オルカンやS&P500などの有名な投資信託はこちらのタイプが多いです。
- 例えば、あなたが同じように100万円分の投資信託を買ったとします。
- 1年間で3万円分の利益が出たとしても、分配金として受け取ることはありません。
- その代わりに、投資信託自体の価値(基準価額)が上昇し、評価額が103万円になります。
- 現金の受け取りはありませんが、評価額がしっかり増えていくイメージです。
2つの違いは「NISA枠の使い方」にも影響する
ここで大切なのが、「NISA枠」をどれだけ使うかという点です。
- 1つ目のパターン(分配金で自動再投資する場合)は、分配金でもらった3万円を再投資すると、その分NISA枠も追加で3万円分使うことになります。
→ 100万円+3万円で、NISA枠を合計103万円分使ったことになります。 - 2つ目のパターン(分配金が出ず基準価額が上がる場合)は、追加でNISA枠を消費することなく、評価額だけが103万円に増えます。
→ 使ったNISA枠は100万円のままで、評価額が103万円になるイメージです。
どちらが有利?NISA枠を最大限活かしたいなら…
将来的にNISA枠(新NISAでは最大1,800万円)をすべて使い切る前提で考えると、
「分配金が発生せず、基準価額が上昇する」タイプの投資信託の方が、より効率的にNISAの非課税メリットを活かせます。
- 分配金が出るたびにNISA枠を消費していくと、限度額に早く到達しやすくなります。
- 逆に、分配金が出ずに自動的に基準価額が上がるタイプなら、同じ評価額でもNISA枠の消費は抑えられます。
そのため、「分配金が出ないタイプ=自動的に基準価額が上昇していく投資信託」を選ぶのがおすすめです。
代表的なものとしては「オルカン」や「S&P500」連動の投資信託などがあります。

こういう観点でもやはり投資信託がおすすめです。
投資信託のメリット・デメリット
- メリット
- 少額から始めやすい
- 自動積立が簡単
- リバランスや分配金の再投資が自動
- つみたてNISA対応商品が多い
- デメリット
- リアルタイムで売買できない
- 運用コスト(信託報酬)がETFより高い場合も
ETFのメリット・デメリット
- メリット
- 株と同じ感覚でリアルタイム売買できる
- 運用コスト(信託報酬)が低めの商品が多い
- 配当(分配金)を現金で受け取りやすい
- 海外ETFにも投資できる(新NISA成長投資枠)
- デメリット
- 購入単価が高くなりがち
- 自動積立が設定できない(または面倒な証券会社も)
- 売買手数料がかかる場合がある
NISA枠を活用するなら投資信託がおすすめ
投資信託とETFは、どちらもNISA枠で非課税のメリットを享受できます。
「コツコツ積み立て」「ほったらかし運用」が希望なら投資信託、「配当金や値動きを楽しみたい」ならETFが向いています。
個人的な意見にはなりますが、投資にはあまり時間やメンタルを割きたくないので、ほったらかしで資産が増えていくという状況が理想です。
オルカンやS&P500などの指数に連動する投資信託であれば、「自動再投資によるNISA枠の有効活用」と「毎月一定額を積み立てることによるドルコスト平均法の則った投資」を両立させることができます。
そういった意味で、無理のない額を積立設定してあとは放置しておける投資信託がおすすめです!
まずはご自身の目的やスタイルに合った商品を選んで、NISA枠を有効活用していきましょう!